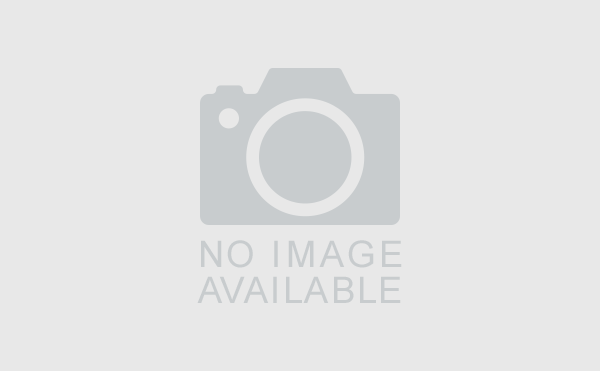Windows版Vimインストール時の付属コマンド

OSによって異なるが,テキストエディターのVimはインストール時にいくつかのコマンドが付属している。気になったので,Windowsで付属しているコマンドを調べた。
Vimのインストーラーの入手方法はいくつかあるが,ここではどの環境でも付属していることを考えて,公式が配布しているVimを対象とした。
公式が配布しているWindows版Vimは以下のサイトからダウンロードできる。
これはインストーラーになっており,特に変更しなければ以下の場所にインストールされる。
C:\Program Files (x86)\vimしたがって,上記ディレクトリ以下で拡張子.exeのファイルを検索すれば,vimに付属のコマンドを見つけることができる。
なお,Vimのヘルプに付属コマンドについて書かれていないか調べてみたが,まとまった記載は見当たらなかった。
Vimのインストールディレクトリを調べたところ,Windows版のvim 7.4には以下の実行ファイルが付属していた。
- uninstall.exe:Vimのアンインストーラー。
- vim.exe:コマンドプロンプトなどのターミナルでの実行ファイル。
- gvim.exe:GUIでの実行ファイル。
- vimrun.exe:WindowsでVimから外部コマンドを実行するときに内部で使用している。
- xxd.exe:バイナリファイルの編集で使用。
- diff.exe:GNU diffutilsのdiff。差分の処理で使用。
vim.exe,gvim.exeはvimの本体であり,またアンインストーラーuninstall.exeが存在することは想定内だった。vimrun.exeというVimから外部コマンドを実行するコマンドがあったのは初めて知った。しかし,これもvim本体機能と考えて良いだろう。
実質的に,Windowsで付属している外部コマンドと呼べるのはxxd.exeとdiff.exeの2個だろう。xxd.exeはバイナリーファイルをVimで扱うために使うコマンドだ。diff.exeはVimで差分を処理するのに使うのだろう。
なお,Windows向けへのビルドについては以下で説明されており,Windowsでインストールされるコマンドについての情報もここに記載されている。
Nullsoft Installation System (NSIS)というWindowsインストーラーを作成する自由ソフトを使っているようだ。
Vimは多機能なテキストエディターなのでもっと外部コマンドも一緒にインストールされるのかと思ったら,2個しかなくてちょっと予想外だった。おそらく,dllなどライブラリとして含めていて,Vim内部からより密接に使えるようになっているのだと思う。
あまりこのような情報はなかったので,ひとまずWindows版のVimをインストールするとxxd.exeとdiff.exeが使えるようになることがわかったので参考になった。